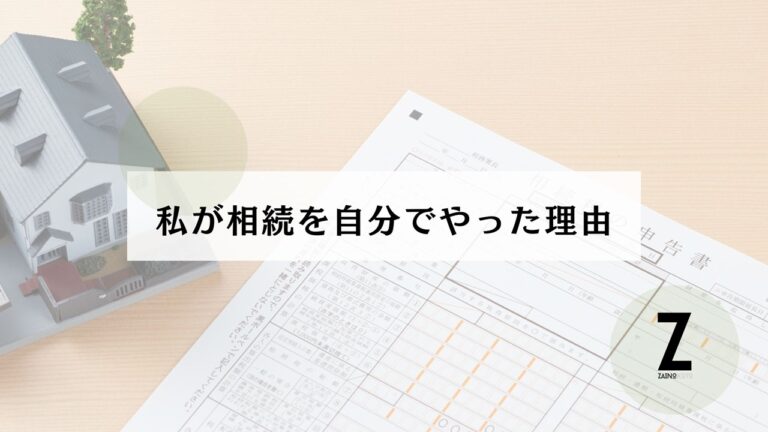〜三代にわたる相続から学んだ「後悔しないための知識」〜
はじめに
こんにちは、SHIMAです。
私は祖母・両親・私たちと三代にわたり、不動産・駐車場経営をしてきた家庭に育ち、現在も家族で不動産管理・運営に携わっています。
これまでに祖母・母・父と3度の相続を経験しました。最初は専門家に任せていた私が、なぜ最終的に自分で相続手続きをするようになったのか――その経緯と学びをお伝えします。
母の相続|公正証書と「やることリスト」でスムーズに
最初の相続は母からでした。
ファイナンシャルプランナーであった母は、生前に公正証書を作成し、亡くなった後に私がやるべきことをリストにして渡してくれていました。
そのおかげで、戸籍の取得や登記申請などの手続きを家族でスムーズに進めることができ、専門家の手を借りずに完了しました。
祖母の相続|プロに任せたはずが…気づいた“違和感”
次に経験したのは祖母の相続。
祖母の確定申告を長年お願いしていた税理士さんに、相続税の申告を依頼しました。
ところが…
✔ 「とりあえず急いで相続税を振り込んでください」と言われる
✔ 納得する間もなく振込を実行
その後、税理士さんから突然、こう言われました。
つまり、養女だった母がすでに亡くなっていても、私(母の実子)に祖母との血縁があるため、私も相続人になれるということ。
珍しいケースとのことで、税理士さんもあとから気づいたそうです。
相続税を抑える工夫は…?助言がなかった理由で決意
さらに税理士さんから提案されたのは、
というもの。
でも、それでは将来、父が亡くなった時に、私たち子どもが相続税を再び支払うことになります。
専門家でも「将来の税負担を減らす提案」はしてくれないことがある。
本気で守りたいなら、自分たちが勉強し、主導権を持つ必要がある。
私は色々と調べ、自ら相続税のシミュレーションを行い、分割の仕方によって税金を抑えられる方法を見つけました。そして税理士さんに訂正をお願いし、納得のいく形に整えることができました。
父の相続|最終的に、すべて自分で手続きを
父の相続の際には、はじめから私が手続きを主導しました。
- 不動産の評価額・小規模宅地の特例を考慮して分割
- 相続人で話し合い、遺産分割協議書を自作
- 戸籍、評価証明書、登記簿などを自分で取得
- 税務署へ相談しながら申告を完了
祖母の時に「人任せではダメだ」と痛感していたため、すべて自力でやりました。
相続から学んだ3つの教訓
1. 相続準備は「生前の備え」がカギ
公正証書ややることリストがあるだけで、家族の負担は大きく軽減されます。
2. 専門家任せでは「抜け」が生まれることも
法律・税務のプロでも、全体最適(家族全体にとってのベスト)は提案してくれるとは限りません。
3. 相続は“今”から学ぶべき
「まだ先の話」と思っていても、相続は突然起こります。知識があることで、冷静に動けるようになります。
まとめ
「相続はプロに任せれば安心」――そう思っていた私が、最終的にすべて自分で手続きを行うようになったのは、自分で学び、考えることでしか守れないものがあると気づいたからです。
✔ 「知らなかった…」では後悔する可能性も
✔ 相続の話題を避けず、日常の延長で話せる空気づくりが大切
⚠️ 免責事項
私は法律家や税理士ではありません。
本記事の内容は、あくまでも私の個人的な実体験に基づく情報です。
実際の相続・登記・税務等については、必ず専門家(税理士・司法書士・弁護士など)にご相談のうえご判断ください。